春の七草って何?どんな覚え方があるの?春の七草粥はどこからきたの?秋の七草とはどう違うの?
1月7日は、特別なお粥、七草粥を食べる日だよね。でも、なぜ1月7日なの?春の七草ってそもそも何?
今回は、春の七草について学んでみよう。春の七草の意味や特徴、覚えやすい方法、秋の七草との違いや、七草粥の起源について、わかりやすく説明するよ!
春の七草 簡単な覚え方はこちら
春の七草の名前を覚えるのは、たしかにちょっと難しいかもしれないね。でも、詩や歌のリズムを使えば、覚えやすくなるよ!
5、7、5、7、7 で覚える!
「5.7.5.7.7」のリズムに合わせて、
「せりなずな/ごぎょうはこべら/ほとけのざすずな/すずしろこれぞ/ななくさ」
と詠んでみよう。歌みたいにリズムをつけると、覚えやすくなるよね。歌の歌詞も、メロディーがあると覚えやすいのと同じだね!
語呂合わせで覚える!
語呂合わせは子供たちにとって覚えやすい方法です!「セナはゴッホとすず2つが好き」というフレーズは、春の七草を楽しく覚えるのに役立ちそうです。
このように、それぞれの草の頭文字を取って作られたフレーズは、子供たちが楽しみながら覚えるのに最適ですね!
どうして春の七草粥を食べるの?
春の七草が選ばれた理由は完全には明らかではないけれど、それぞれの草には特別な意味があると言われているんだよ。
セリ(芹)

邪気を払う力があるとされている。
ナズナ(薺)
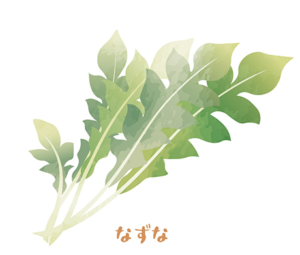
身を守る、健康を保つという意味がある。
ゴギョウ(御形)

魔除けや厄払いに役立つとされる。
ハコベラ(繁縷)

家族の絆を強めると言われている。
ホトケノザ(仏の座)

幸運や長寿をもたらすとされる。
スズナ(菘)

根強い生命力を象徴し、健康や成長を願う。
スズシロ(蘿蔔)

純粋や清らかさを表し、心身の浄化を象徴する。
これらの草を七草粥に入れて食べることで、新年の健康や幸福を願うんだね。
七草粥を食べる由来って?
七草粥の歴史は、中国の古い習慣と日本の文化が融合して生まれたものだね。
- 中国では新年に各日に動物を当てはめ、運勢を占っていた。特に1月7日は「人の日」とされ、七種類の野菜を使った「七種菜羹」を食べて、無病息災や出世を願っていたんだ。
- 日本では、若い野菜を摘んで食べる「若芽摘み」の習慣や、1月15日に七種の穀物を食べる風習があった。
- これらの習慣が組み合わさって、七草粥という形になったと考えられているよ。
- 江戸時代には、幕府が1月7日を人日の節句と定めたことで、七草粥が一般の人々の間にも広がっていったんだ。
このように、七草粥は中国の伝統と日本の文化が合わさって、今日に至るまで大切にされている行事食なんだね。
春の七草の種類と特徴
春の七草はそれぞれ独自の特徴と栄養があり、健康に役立つんだね。それでは、一つずつ見てみよう!
セリ

セリ科の植物で、独特の香りが特徴。胃腸を強くし、解熱、食欲促進、利尿作用、血圧を下げる効果があります。ビタミンA、C、カリウムが豊富。
ナズナ(ぺんぺん草)
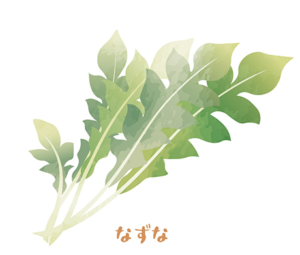
道端によく見られる草。利尿、止血、解毒作用があるとされ、ビタミンKを多く含んでいます。
ゴギョウ

キク科の植物。咳、痰、喉の痛みの改善に役立ち、昔から草餅にも使われていました。
ハコベラ

ナデシコ科の植物で、利尿、止血、鎮痛作用があります。ビタミンA、B群、C、カリウム、カロテノイド、サポニンが豊富。
ホトケノザ

キク科の植物で、健胃や食欲増進に効果があります。食物繊維が多く、整腸作用も期待できます。
スズナ(カブ)

アブラナ科の植物。ビタミンA、B、Cが豊富で、鉄やカルシウムなどのミネラルも多く含まれています。胃腸や肌の調子を整える効果があります。
スズシロ(大根)

ビタミンA、C、食物繊維、消化酵素(ジアスターゼ、アミラーゼ)が豊富。胃腸の調子を整え、風邪の予防にも効果的です。
それぞれの草には健康に良い多くの効果があることがわかるね。七草粥にこれらを入れることで、体に良い影響をもたらすんだね。
春の七草と秋の七草の違い
秋の七草についての説明、面白いね!秋の七草は春の七草と違って食べるためではなく、美しさを楽しむためのものだね。それぞれの草には独自の歴史や意味があるようだよ。詳しく見てみよう:
はぎ(萩)
秋のお彼岸に咲くことから、この時期のおはぎが名付けられました。春のお彼岸には牡丹が咲くことからぼた餅が食べられるんだね。
ききょう
武将の家紋によく使われ、花言葉には「誠実」「気品」「清楚」などがあります。
くず(葛)
食用にも使われる植物で、葛根は乾燥させて漢方薬にも使われます。
ふじばかま
香りが強く、昔は貴族がお風呂に入れたり、香水の代わりに使われていたそうです。
おみなえし(女郎花)
名前の由来は「美女を圧倒するほどの美しさ」。利尿や鎮痛作用があるとして漢方薬にも使われています。
おばな(すすき)
十五夜のお供えに使われるすすきの別名です。
なでしこ
「大和撫子」という言葉はこの花から来ています。
秋の七草は、その美しさや歴史、薬用としての利用など、様々な側面を持っていて、日本の文化や自然と深く関わっていることがわかるね。
秋の七草の簡単な覚え方は?
秋の七草を覚えるための「5.7.5.7.7」リズムのアイデア、素晴らしいね!このリズムに合わせて、「はぎききょう/くずふじばかま/おみなえし/おばななでしこ/秋の七草」と詠むと、確かに覚えやすくなりそうだよ。
リズムに合わせて繰り返し読むことで、秋の七草の名前を楽しく覚えることができるね。歌や詩のようにリズムをつけると、記憶に残りやすいから、秋の七草を覚えたいときにぜひ試してみてほしいね!
まとめ
春の七草粥は、1月7日の人日の節句に食べる伝統的な日本の行事食だね。昔は無病息災を願って食べられていたけれど、現代では年末年始の重い食事の後に胃腸を休めるためにも食べられているんだね。
一方で、秋の七草は春の七草と違い、食用ではなく、その美しさを楽しむためのもの。秋の七草は観賞用として楽しまれ、日本の自然や文化の美を象徴しているね。
春の七草粥を食べる習慣は、日本の伝統的な暮らしや、季節に合わせた健康の知恵を表していると言えるね。


